日銀がマイナス金利という未踏の領域に踏み出しました。当初は株価が急騰し、為替市場では1ドル=120円台を付ける場面もあったのですが、その後、マイナス金利に対する期待は急速に萎み、再び113円台まで戻ってしまいました。
本来であれば、マイナス金利政策は量的緩和策を後押しするものであり、当然、円安と株高が期待されるところです。米国株が軟調というタイミングの悪さもありますが、ここは別の要因が働いていると考えた方が自然でしょう。
今回の市場の動きが、これまで明示的に意識されていなかった政策コストが顕在化した結果なのだとすると、状況は深刻です。
リスク資産にお金は向かわず、現金をさらに退蔵
日銀が導入したマイナス金利政策とは、金融機関から預かっている当座預金の一部に対してマイナスの金利を付与するというものです。実際にマイナス金利が適用されるのは、既存の当座預金残高ではなく、これから日銀が購入する国債の代金分からです。
しかし、銀行にとっては、これまで預けていれば金利がもらえたものがなくなってしまうわけですから、当然のことながらこれに代わる収益源を探し出す必要に迫られます。つまりマイナス金利政策とは、銀行が当座預金にお金を預け続けると損をするように設定することで、お金を市中に流通させることが狙いということになります。
ところが、銀行は日銀が想定したようには行動しない可能性が高くなってきました。マイナス金利の導入が決まるとすぐに、預金者の負担でその損失を回避しようという動きが出てきていることからもそれが分かります。
メガバンクや地方銀行の中には早くも普通預金や定期預金の金利を引き下げたところがあるほか、銀行側が正式に発表したわけではないものの、大企業の預金口座から手数料を徴収することを検討しているとの報道もありました。リスク資産に資金を配分するのではなく、現金を温存し、取れるところからお金を取ろうという方向性のようです。
市場の動きも同様でした。株式や外債などリスク資産に資金が向かうことは想定されず、当初の狙いとは正反対に円高と株安が進んでいます。株安については、米国の株価下落に引きずられた可能性が高いですが、急激な円高はやはり日本市場では現金が退蔵されることを見越した動きと解釈してよいでしょう。
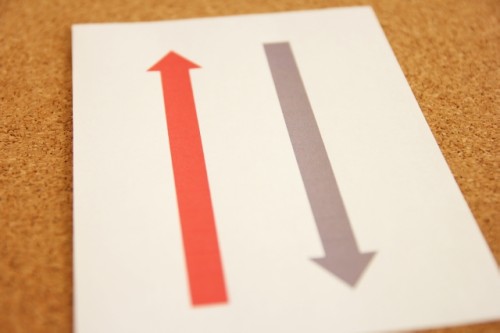
日本人は量的緩和策の政策コストを認識していなかった?
このように理論とは真逆の動きになってしまった背景にあるのは、おそらく国民の政策コストに対する認識不足でしょう。あらゆる政策にはメリットとデメリットがあり、タダで効果が得られるわけではありません(いわゆるフリーランチは存在しません)。
しかし量的緩和策は一見、コストがかからないように見えるという特徴があり、これがマイナス金利の導入によって一気に崩れてしまったのです。
かつて日本政府は大量の国債を発行し、大型の公共事業を継続していました。しかし日本の財政問題がクローズアップされたことで、無尽蔵な公共事業に対しては批判が集まるようになりました。小泉内閣では、こうした国民の声に応え、構造改革によって日本を成長軌道に乗せようという試みが行われました。
財政政策には政府債務の増大というコストがあり、構造改革には、既得権益を持った人の利益が失われるというコストが存在します。結局、構造改革も日本国民の総意で中断という結論になったわけですが、一連の政策がストップしてしまったのは、いずれも目に見える形で、政策コストが強く意識された結果と考えることが可能です。
財政政策もできない、構造改革もできないという状況で、彗星のように登場してきたのが量的緩和策です。この政策は、日銀が国債を購入するだけですから、一見、大きな国民負担は生じないように見えます。しかし現実には量的緩和策にもコストは発生します。
もしインフレが進んだ場合には、現金の価値が減価することになりますから、運用せずに貯金していた人の資産が目減りします。インフレ政策は、預金者から税金を取ることと同じですから、インフレ課税と言い換えることも可能です。
しかし量的緩和策については、財政政策や構造改革と比べてイメージがしにくく、預金者の負担で行う政策であるという認識は希薄でした。ところが、量的緩和策の延長線上にあるはずのマイナス金利政策は、預金者の負担というコストを強く認識させる結果となってしまったようです。
量的緩和策もマイナス金利も、預金者の負担という点では同じですが、市場の反応はそうではありません。もし従来の政策と同様、景気回復のためにコストを払いたくないということが続くのであれば、日本経済にはもはや打つ手がなくなってしまいます。
「フリーランチは存在しない」という原理原則を認識することは大事なことですが、もしかすると、すでに時は遅すぎたのかもしれません。

